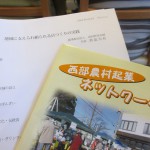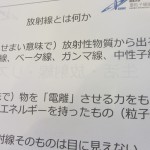今日は、昨年に引き続き、ヨシナガ・アカデミーに参加させていただきました。
今年は3名の方の発表がありました。
まず一人目は、国分野菜本舗の真塩光江枝さん。
地産地消に取り組んでというテーマで、
女性就農者の視点で、農業の未来について語っていただきました。
男性就農者が圧倒的に多い中で、先頭になって国分野菜を売り込んでいる真塩さんのアイデアやパワーは本当に素敵です。
後で頂いた国分人参ジュースは、絶品でした★
二人目は、群馬大学重粒子線医学研究センターの鳥飼幸太先生。
何度かお会いしたことがありますが、
今日の「生活・放射能・リスク」という講演では、
私たちが生活するうえで、放射能やさまざまなリスクとどのようにむきあっていくか、
自分たちでしっかりと判断していくことの大切さを改めて考えることができました。
3人目は、高崎市教育委員会文化財保護課の若狭徹さん。
先日、委員会調査でお世話になったばかりですが、
今日も、古代高崎の渡来文化について、わかりやすくそして楽しく説明していただきました。
女性の未来、現代のテクノロジー、古代文化という
全く分野の違う3名の方のお話を聞きながら、
やはりいろいろなアンテナを張っておくことは人生を豊かにするなぁ、と感じました。
専門分野を突き詰めることも大切かもしれませんが、
ちょっと違った角度から物事を考えたり、
新しい発想のチャンスは、様々な知識・経験から生まれてくるのだと思います。