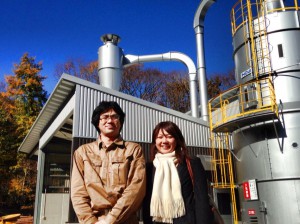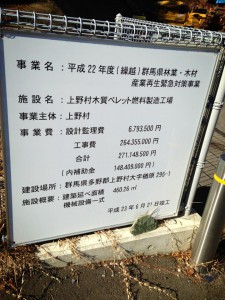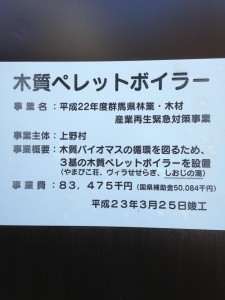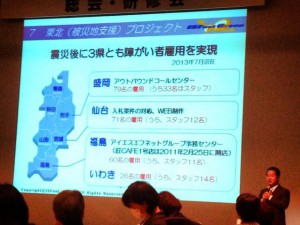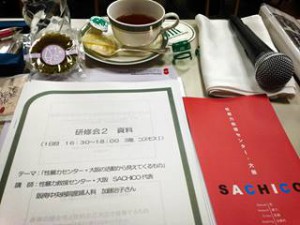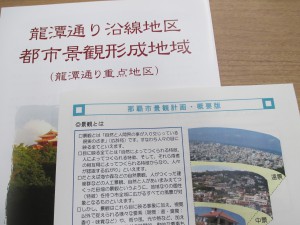小川あきら です。
2日めの調査は、国立劇場沖縄から。
こちらは、国の重要無形文化財に指定されている組踊をはじめとする
沖縄の伝統芸能の保存振興を図る目的で開場した全国で5番目の国立劇場です。
高崎市が計画している文化芸術センター機能を中心とする都市集客施設と
県のコンベンション施設の機能分担や相互連携の参考とするために、
施設の利用状況等を調査しました。
大劇場は約600席で演者の地声が響く広さとなっており、
沖縄伝統文化に特化した劇場になっています。
国立劇場ということで、維持管理には国費が投入されていますが、
その金額は人件費を含め年間6億2000万円とのこと。
ハコモノの維持には相当な金額がかかることを改めて実感しました。
高崎市の都市集客施設でも群馬県のコンベンションセンターにおいても
相当な維持管理費がかかることが予想されましが、
単純に指定管理やPFIなどで外部に委託するだけでクリアできる問題とは思えません。
県のコンベンションセンターの設置に関しては、県民の皆様から、
「必要性がない」「無駄なハコモノ」「税金のもっと有効な使い道がある」
「今最優先にしなければならないこととは、到底思えない」
「作ったあとにも税金を垂れ流すことになる」など、様々な意見をいただきました。
(もちろん賛成する方もいると思いますが、
私のところには反対意見の方がたくさん集まっています。)
今後の委員会の中でも、しっかり議論していきたいと思います。





引き続いて、那覇市役所へ。
那覇市では、古くから都市景観条例に基づいて、那覇の個性を活かした
美しいまちづくりを進めていることから、その取り組みについて調査をしました。
首里城周辺の伝統的な建造物が一体となった地域を都市景観形成地域として指定し、
首里城にマッチするように、建物の高さ制限、屋根の色の制限(オレンジの瓦屋根)、
壁の色の制限(コーラルホワイト)、敷地の素材の制限(石畳風にすること)など、
本当に街の雰囲気ががらっとかわるような都市形成をしています。
このような大掛かりな変更には、行政からの一方的なアプローチでは難しいだろうな、
と思っていたら、やはり住民のみなさんの強力な後押しがあったとのこと。
例えば、地域住民の皆さんがコンビニに働きかけをして、店舗の色を変えてもらったり、
看板を低くしてもらうようにお願いしてくれたそうです。

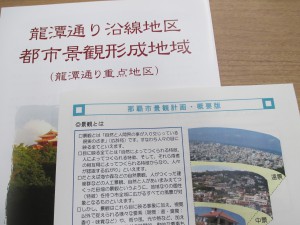
実際に龍潬通りを案内してもらいました。

 歩道が広く、石張りになっています。
歩道が広く、石張りになっています。
 交番も、オレンジ瓦にホワイトの壁、石畳です。
交番も、オレンジ瓦にホワイトの壁、石畳です。
 コンビニも。
コンビニも。
 郵便局も。
郵便局も。

群馬県内では、桐生市でのこぎり屋根を活かしたまちづくりをしていますが、
各地域で同じように個性を活かしながら、
自然や文化と一体となったまちづくりを推進していきたいですね!
ついでに、昨年度建て替えたばかりの那覇市役所。

四角い建物だと街に圧迫感がでるという理由から、斜めのデザインになっており、
将来的に外壁はグリーンカーテンで全て覆われるそうです。
市議会の議場は円形議場。

赤ちゃんや子供連れでも膨張できるように、防音の傍聴ルームも用意されています。