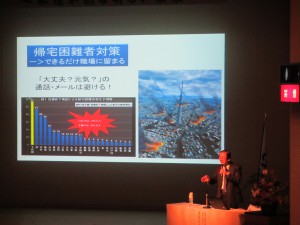小川あきら です。
本日、今年度最後となる放射能対策特別委員会の審査が行われました。
震災から2年。
放射能とのかかわりは、今後も長く続きますが、
この2年で県民の皆さんの関心が少しずつ減ってきているような気がして、
とても心配です。
今日の委員会では、原子力発電所の安全確保にかかる連絡体制について、
東京電力との覚書が締結されたことや、群馬県放射線マップの公開について
報告がなされたほか、最終日も本当に沢山の質疑が行われました。
私からは以下の点について、質問と要望をさせていただきました。
・指定廃棄物が最終処分場完成までの間、フレコンバッグにいれられて保管されているが、フレコンバッグの耐用年数は、1年~3年といわれている。既に震災から2年が経過し、保管状況によってはバックの劣化が早まることから、指定廃棄物の保管状況の確認と、適切な管理方法を検討すべきではないか。
・六ヶ所村の最終処分場では、低線量の放射性廃棄物を、ドラム缶に入れて、コンクリート詰めにし、最終的に土で覆うという処理をしているので、最も安全に保管するのであれば、群馬県でも同じような保管方法を検討すべきではないか。
・学校や公園とうの公共施設における除染作業の進捗状況について。環境省の発表では、群馬県の除染作業については、教育施設は、計画の対象だった23施設のすべてで終了しているものの、公園・スポーツ施設は除染予定28施設のうち17施設(61%)、農地は53・3ヘクタール中の16・8ヘクタール(31%)、森林は6ヘクタール中の1ヘクタール(17%)の進捗状況となっている。今後のスケジュールはどのようになっているか。また、公園やスポーツ施設は子どもたちも利用するところなので、除染が終了した施設と、そうでない施設がわかるようにしてもらいたい。
・「ぐんま食の安全情報」に関連して、野生の動物やきのこ、山菜、川魚などでは出荷停止になっているものが多くある。にもかかわらず、県の発表する安全情報に「注意してください」という記載しかないのは、注意喚起としては弱い。食を控えるなど分かりやすい表現に工夫してもらいたい。
本日をもって、委員会として付議されている事件についての審査は全て終了となります。
特別委員会としては、本年度で解散となりますが、
今後も所管の常任委員会の中で放射能に関する問題や情報については、
注意深く見ていきたいと思います。