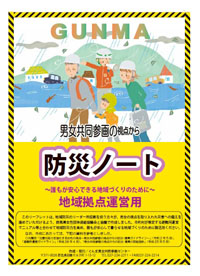県外調査2日目、午前中は【熊本県医療的ケア児支援センター】にお邪魔しました。
熊本県では全国に先駆けて2016年から熊本大学病院内に小児在宅医療支援センターを開設し、保育所や学校への入園・入学支援、関係者の人材育成などの医療的ケア児の支援を実施してきましたが、今年の4月からは熊本大学病院を医療的ケア児等支援法に基づく【医療的ケア児支援センター】として指定し、二枚看板で医療的ケア児とその家族が地域で安心して暮らせるよう、相談対応や地域支援体制の充実に取り組んでいるとのこと。
支援のポイントは4課連携。
保健師(母子保健担当)、保育所管課、教育委員会、障害福祉が連動して支援体制を整備することが大切で、市町村が医療的ケア児等コーディネーターの配置や、就学・入園支援、看護師育成などを行う際に、各機関を切れ目なくつなぐ包括的な役割を熊本県医療的ケア児支援センターが担っているそうです。
法律上の根拠に基づく支援センターとして位置付けられたことで、今までよりも市町村への働きかけがしやすくなったものの、医療的ケア児等コーディネーターが配置されている市町村は6市町村に留まっており、市町村によっては思うように体制整備が進んでいないのが課題で、市町村向けの研修会や各医療県域ごとの看護師のスキルアップ研修などにも説教的に取り組んでいるとのこと。
医療的ケア児支援センターは今年度中に39の都道府県で開設される予定で、群馬県としても早期の設置を目指したいところ。
(現状では保護者が相談先を見つけにくかったり、窓口でたらい回しにされたりするケースもあります…)
母子保健、障害福祉、保育、教育、そして就労まで、県と市町村が責任を持って支援できるように、先進県の取り組みを群馬でもしっかり活かしていきたいです!